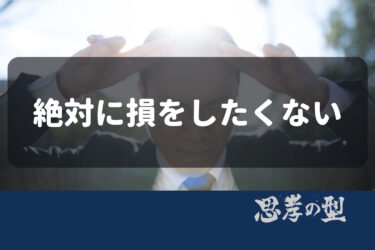ヒカリ
ヒカリ ナメリーヌ
ナメリーヌ ヒカリ
ヒカリ ナメリーヌ
ナメリーヌ ヒカリ
ヒカリ ヒカリ
ヒカリ損失回避性とは
損失回避性とは、「利益による満足感」よりも「損失による苦痛」の方が心理的インパクトが大きいために、「利益拡大」よりも「損失回避」を優先する心理現象を言います。
なぜ、損失回避性は機能する?
損失回避性は、なぜ機能するのでしょうか?
それは、私たちの脳の中にある「扁桃核(へんとうかく)」と呼ばれる部位が関わっています。
扁桃核は、人間の「恐怖」「不安」といった感情を決める場所であり、人間の仕組みにおいて、「損失=死亡」につながる事から、「損失」に対してはこの扁桃核が過剰に反応するため、人は損失を嫌う、と考えられています。
また、人は未来のことよりも現在を優先しようとする「現在バイアス」が心理的に作用するため、今目の前にある「損失」への恐怖が高まりやすいとも言われています。
人は「損」を嫌う。そして、結果的に損をする。
先に説明した通り、私たちは損を嫌います。
例えば、明日までの期限でネット通販のポイントが200ポイントあったとしましょう。
本来ならば、本当に欲しいものがなければ、何も買わないのが一番です。
ですが、私たちは「明日までに使わなければ!」と考え、大して欲しくないものを買ってしまうのです・・・。
損だけを嫌うのはナンセンス
損失だからと言って単純に嫌うことはナンセンスです。今、損失を出すことで将来の利益拡大につながる事もあるのです。
例えば、自己研鑽です。
講習会や自己啓発などの自己投資(一時的な損失)を行うことで、出世や人脈の拡大(利益獲得)につながる事もあります。
行き着くところ
ただ損失をだけを嫌っていけば、その先に得られる利益も失うことになり、結果的にそれが「損失」となります。
今支払う損失に対して単純に嫌うのではなく、将来に何を得られるかを考えてみる事が大切です。
身近にある損失回避性の罠
ここまで損失回避性について解説してきました。
この損失回避性を利用して、私たち消費者に対してたくさんの罠が仕掛けられています。
私たちは無意識のうちにこの罠にかかり、論理的ではない選択をしてしまう事もあります。
期間限定
まずは「期間限定」です。
「ここを逃したら2度と買えない!」という消費者の損失回避性に働きかけます。
あなたも大して欲しくもないのに、期間限定に負けて購入してしまった経験があるのではないでしょうか?
数量限定
次は、「数量限定」です。
「期間限定」に似ています。
「今買わないと、売り切れてしまう!」という消費者の損失回避性に働きかけます。
こちらは「希少性の原理」とのコンボになっており、タチが悪いですよね。
直接的な訴求
最後は「直接的な訴求」です。
食器用洗剤を例にすると、「食器には雑菌がいっぱい!」といったように「あなたは常に損をしていますよ」と訴えかける手法です。
消費者は損失を嫌がるために、食器用洗剤を購入して損失を回避しようとするのです。
まとめ
- 損失回避性とは、「利益拡大」よりも「損失回避」を優先する心理現象のこと
- 損卒回避性は、扁桃核が反応することにより機能する
- 私たちの身近には、損失回避性を利用した罠がたくさん潜んでいる