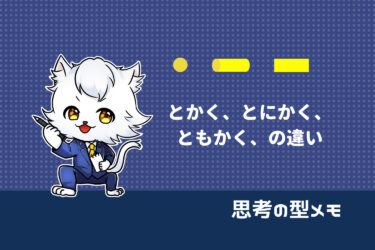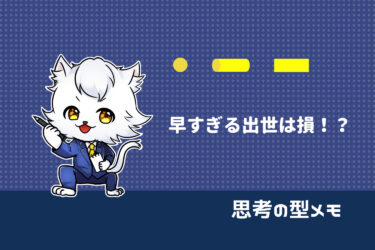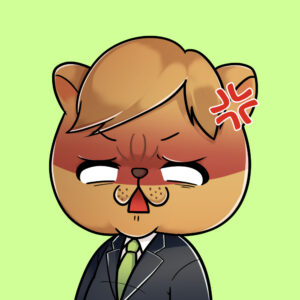 ナメリーヌ
ナメリーヌ ヒカリ
ヒカリ ナメリーヌ
ナメリーヌ相手と意見が食い違ったとき、あなたは上手く「反論」することが出来ますか?
相手に言われっぱなしで何も言えなくなってしまう人や、「反論」の仕方を間違えて人間関係を壊してしまう人もいるでしょう。
悔しい!悔しくないですか!それは! どうせなら上手く「反論」して自分の主張を通したい!!
自分の本音を殺すのはもう嫌だ!!
そんなあなたに、この記事を見てほしい。そして、負けない反論をしましょう!
反論の心得
反論とは
まず初めに反論とは何か。
反論とは「口喧嘩」や「罵倒」ではありません。
多くの人は「反論」すれば人間関係を壊すと考えているでしょうが、実はその逆で、自分と相手の意見の違いをはっきりとさせて、お互いの価値観を認め合った上で、信頼関係を深めることが出来る優秀な手段なのです。
だからあなたも恐れず、気軽に「反論」を行ってほしい。そして相手と良好な関係を築いてください。
目的を見失わない
さて、そんな反論についてですが、目的を見失ってはいけません。
先ほども申したように、好き勝手に反論して、相手との人間関係を壊すことが目的ではありません。
反論の目的は、相手に自分の主張を理解してもらい、信頼関係を築くことです。
なので、「絶対に譲れない」ものは何かを決めておけば、反論することが楽になるし、前もって準備することができます。
また、信頼関係を築くにあたって、相手への誠意も忘れてはいけません。
反論のメリット
疑う力が身に付く
思考停止してイエスマンになるのことだけは、絶対にNGです。
他人の意見・情報・データ、そのほとんどにバイアス(偏り)がかかっています。どんなバイアスがかかっているか常に考え、即座に見抜けるようになることが重要です。
具体的には「根拠と主張が合っていない」ことや、「根拠による情報が少なすぎないか」といったことに注目して疑うことが大切です。
こういった思考を「クリティカルシンキング」と言うので覚えておきましょう。
一目置かれる存在になる
存在感がない人ってどんな人でしょう。
- 意見を言わない
- あまり喋らない
- 自分に自信がない
- 頼りがいがない
だいたいこんな感じの特徴ではないでしょうか。
反論できるようになるってことは、これらの特徴と真逆になるということです。
人は、自分の意見と違う主張をしてくる人に対して、意識しやすい生き物です。
なので、自分の意見を主張できて、反論できる人は、相手の記憶に強く残ることが出来るでしょう。
判断力が高まる
反論をしない=イエスマンということになります。
反論をしっかり出来るようになる、とはその逆で、自分で物事を考え、自分の意見をしっかり相手に伝える事ができるということです。
常に自分で考えることで、判断力が磨かれ、判断にかかるスピード&クオリティは反論を行うほど向上していきます。
反論術
ここから具体的に反論術を解説していきます。
反論のルール
思考停止タイプは相手にしない
思考停止タイプの人は、何も考えずに発言します。そんなタイプと議論するのは、時間のムダになります。
例えば次のような会話が見られたら、聞き流すようにした方が良いでしょう。
 モブ
モブ ヒカリ
ヒカリ モブ
モブ昔から紙の本を読んできたからだよ
全ての人が、自分の考えを確立しているわけではありません。上記の会話のように、何も考えずに発言する人はたくさんいます。そんな人とは議論が成立しないので、相手にしてはいけません。
相手の話は、最後まで聞こう
コチラの話を最後まで聞かずに、意見を主張してくる人と議論した経験はあるでしょうか。
そういった人は、相手の話を聞いている最中に「次に自分はどういう質問をぶつけようか」などと考え、どうやってマウントを取るかを常に考えています。
経験者なら分かるでしょうが、そういった態度で話を聞かれるのは非常に不愉快ですよね。
だから自分も相手の話や主張を最後まで聞いてあげる必要があるのです。
ここで話の途中で「それは違う!」等と強引に割り込むと、相手は「俺の話はまだ終わっていないのに!!」という気持ちになり、反発心を持つようになります。
一度、反発心を持たれると、相手にこちらの主張を受け入れもらうことは難しくなるでしょう。
言葉というものは不思議なもので、「何を言ったか」は、さほど重要ではなく、「誰が言ったか」と「どんな言い方をしたか」の方が受け入れてもらうためには、重要なのです。
無知を隠さない
人は、自分をかっこよく見せたいという心理から、知らないことも知ったかぶりをしてしまいます。しかし、自分が無知であるにも関わらず、知ったかぶりをしてしまうと反論することが難しくなってしまいます。
例えば、
 ナメリーヌ
ナメリーヌ モブ上司
モブ上司 ナメリーヌ
ナメリーヌこういった感じで知ったかぶりをしてしまうと、反論の余地がなくなってしまいます。
では、どうすれば良いのでしょうか。こういった場合には次のような対応が必要です。
 ヒカリ
ヒカリ モブ上司
モブ上司 ヒカリ
ヒカリ モブ上司
モブ上司 ヒカリ
ヒカリ モブ上司
モブ上司無知を恥ずかしいと思ってはいけない。誰でも知らないことはある。
やるべきことは、知らないという事実をあなたが認め、相手に素直に教えてもらうことです。
「常識じゃないか」
「誰でも知っている」
こんなまやかしな論法に騙されずに、自分の無知を受け入れて反論の難易度をグッと下げましょう。
言葉以外でも反論は成立する
反論は言葉以外でも成立します。
これは、ある会社での出来事です。Sさんと、その他の社員がいました。Sさんは能動的に物事を改善しようとする、やる気のあるタイプです。他の社員はやる気がなく、Sさんに頼りっぱなしで、自分たちは行動は起こさないくせに、Sさんに対して文句を言っているだけの日々でした。
Sさんは言葉で反論して、他の社員を従わせても良かったのですが、あえてそれをせずに次のような行動に出ました。
能動的に物事を改善することをやめたのです。
仕事のムダが放置されることで、次第に他の社員の業務量は増えていき、退職者も多く出て、それがさらに業務量の増加につながるといった負のスパイラルが起き始めました。
そんな状況に我慢できず、他の社員はSさんに謝罪をし、自分たちも積極的に改善に参加するようになりました。
このように「行動」とその後に起きる「事実」によって相手に対して反論することも出来るのです。
言葉にすると相手の反感を買うことでも、行動による反論では人間関係を壊す事がなくなるのです。
「どうしても相手へ反論したいけど、口頭ではちょっと・・・」って時に、ぜひ試してください。
可能な限りの根拠を集める
議論で有利になるには、可能な限りの「根拠」が必要である。表現方法や口達者よりも「根拠」をどれだけ集められるかが鍵となるのです。
「アイツのことが嫌いだから」
「男なら根性で乗り切れ!!」
こんな感情論や根性論(精神論)では相手に勝つのは難しいでしょう。
だから普段から「根拠」となるものを探しておきましょう。
人の心理を利用する
禁止ではなく、指導する
人は禁止されると、逆らいたくなります。
「絶対押すなよ!」と言われているボタンがあったらアナタは押すことを我慢できるでしょうか。私は無理です。
禁止されれば禁止されるほどやってみたくなる心理現象・・・これを「カリギュラ効果」と呼びます。
このカリギュラ効果を発動させないためにも、誰かに注意する時には「~はダメ!」だとか「~するな」と言う語尾は使わないようにしよう。反発されて、こちらの主張を受け入れてくれなくなります。
だから同じ注意でも「~しなさい」といった語尾を使用して、禁止ではなく、指導することを意識しましょう。
具体例としては、
「走らないで!!」ではなく、「歩くようにしよう」といった具合です。
表現を置き換える
物は言いよう。同じことでも言い方によって、良くも悪くも印象が変わるのです。
例えば「古い服」を例にすると、次のような言い換えが出来ます。
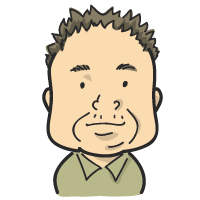 モブ
モブ ヒカリ
ヒカリこういった反論技術を「表現置換法」と言います。
弱点を即座に長所に変えて反論すれば、怖いものなんてありません。
共感して相手の感情をコントロールする
相手が怒ったら、共感して相手の怒りを抑え込みましょう。
ただ謝るってことではないですよ?
例えば、感情をぶつけてきた相手に「アナタのお気持ちはよく分かります」と言って共感するのです。
そして、続けて「しかし、論理的に考えると・・・」っとこんな感じで切り返すのです。
相手の感情をコントロールしつつ、反論を加えられるので、まさに一石二鳥です。
言葉は「早く」「低く」伝える
議論をするときは、早口である方が有利です。早口の方が、同じ時間でも伝達できる情報が多い。情報が多いということは、議論に勝つ確率が高くなるということです。
また早口だと、自信に満ち溢れた話し方になるので相手への説得効果も高まります。
そして、声の高さも「高い」よりも「低い」方が信頼されやすいといった心理効果を与えることが出来ます。
なので、議論をする時は、「早く」「低く」を意識して伝えることが重要なのです。
普段から相手の反発心を奪っておく
いきなり仲良くもない相手から頼み事をされても、快く受ける人はいませんよね。だからこそ普段から、相手の反発心を奪っておく必要があります。
 ヒカリ
ヒカリだとか
 ヒカリ
ヒカリなど、普段からこういった小さな頼み事を積み重ねて、自分からの頼み事に違和感なく従ってもらえるように洗脳(言葉が悪いですが)しておくことが重要です。
このように相手が自分の行動などに対して、一貫したいと思う心理を「一貫性の原理」と呼びます。また、こういった人間の心理を利用して、徐々に小さいものから大きい要求に変えていく心理テクニックを「フット・イン・ザ・ドア」と呼びます。
罠をはっておく
あらかじめ、罠を用意しておき、相手が文句を言いにくい状況を作ったり、相手をその罠に誘導して反論するというテクニックもあります。
突貫で資料を作成したとき、その資料のクオリティはなかなか低いものでしょう。
そんなとき、アナタが上司の立場だったらどこを指摘するか、事前に考えておくと良いのです。
突貫で仕上げた資料であるならば、「この後、清書するつもりですが、先に内容のご確認をして頂けないでしょうか」と伝えておくことで、相手も内容の指摘をしづらくなります。
また、データの信頼度が低いといった問題を、指摘される可能性が高い資料であるならば、そう指摘された時に反論する内容を考えておくと、テンパることなくスマートに反論する事ができます。
浮かれ気分にさせておく
人間は単純な生き物であり、ボーナスが支給されたとか、意中の女性が食事に応じてくれたとか、そんなちょっとした出来事でご機嫌になり、浮かれ気分になります。
そしてそんな「浮かれ気分」の時というのは、心がオープンな状態となっており、他人の要求を受け入れやすくなっているのです。
つまり、ここで意識しなければならないのは、相手が「浮かれ気分」な時に議論に持っていく、という事です。
逆にやってはいけないのは、相手の機嫌が悪い時に議論に持っていく事です。
どんなに正論を述べても感情論で返されてしまう事でしょう。こうなったら話し合いが通じる相手ではなくなってしまいます。
楽な姿勢にさせる
相手に楽な姿勢をとらせよう。
何故なら、人は楽な姿勢をとっている時は、説得に応じやすいからです。
リラックスするという事は、心がオープンになっている状況です。
だから可能な限り、相手に楽な姿勢をとらせることで立場を有利にする事が出来ます。
夕方をねらえ
議論は夕方を狙った方が有利です。
何故なら夕方は、人間の判断力や思考力が最も落ちる時間帯だからです。
・・・洗脳しやすのです。
これを「黄昏効果」というのですが、相手が年配者であればあるほど、黄昏効果は絶大でこちらに有利に働きます。
数字で示す
「数字」には魔力があり、「数字」は人を惑わせるマジックです。だからこそ使い方をマスターすれば、議論で負けなしになるのです。
例えば次のフレーズを比べてみましょう。
- ①「+10%の効果があります」
- ②「1.1倍の効果があります」
- ③「110%の効果があります」
これ、全て同じ意味であるにも関わらず、③「110%の効果があります」が一番効果があるように聞こえませんか?
なので、こういった場合は一番効果がありそうな言い方をしましょう。
また、「この商品は20%の使用者が推奨しています」と聞くと、優秀な商品と錯覚してしまいますが、これは「この商品は80%の使用者が推奨していない」と同義でもあるし、「この商品は5人に1人が推奨している」と同義なのです。
このカラクリを知っていれば、相手を説得しやすくなりますし、相手の数字のマジックにも騙されなくなります。
強敵への反論
極論は例外で潰す
「このプロジェクトが失敗することなど絶対にない!」「この仕事を受ければ絶対に儲かる!」
こういった「絶対」「必ず」「例外なく」といった言葉を使用した極論は、簡単に潰せます。
例えば「この仕事を受ければ絶対に儲かる!」この言葉に対しては、「前回、同じ仕事を受けたが赤字でしたよ」で論破完了です。
また、次のような反論方法もあります。
 モブ上司
モブ上司 ヒカリ
ヒカリ モブ上司
モブ上司このように「絶対」「必ず」「例外なく」言葉を聞き返してしまえば良いのです。
相手は聞き返されることで冷静になり、自分が極論を言っていることに気付かされます。
相手の選択にのらない
2つの選択肢を示して、相手の意見を誘導する「二者択一法」という手法があります。
二者択一法とは、その名の通り二者択一で質問して、相手の意見をどちらかに絞り込むといったものです。
人は選択肢を示されると、つい選択肢の中から回答してしまうそうです。
相手にこの手法を使われて咄嗟に答えてしまうと、そこから反論するのは難しいです。
例えば「会社に人生を捧げるか、会社を辞めるか選べ!」という言葉ですが、この言葉には、
「会社に人生を捧げる」か「会社を辞める」という二者択一法が使われており、咄嗟にどちらかを答えてしまう人も多いのではないでしょうか。
冷静になって考えると、この選択はかなり不利なものなので、この選択肢から選んでしまうと相手の誘導に引っかかってしまいます。
なので、絶対にこの手法にのってはいけません。
では、どうするかというと、この選択肢以外の回答を行うのです。
「会社に人生を捧げるか、会社を辞めるか選べ!」と言われたら、「会社に人生を捧げる」でもなく、「会社を辞める」でもなく、第三の答えを言ってください。
例えば、「会社が私の一生を守ってくれる訳ではないので、人生を捧げるのは難しいですが、私が食べていくために、会社を辞める訳にもいきません」と言えば、相手の誘導を回避することが出来ます。
物事は白黒つければ良いってことではなく、グレーにしておくことも大切なのです。
逃げ道を用意しておく
相手を追い詰めすぎないようにして、必ず逃げ道を残しておきましょう。
「窮鼠猫を噛む」という言葉もある通り、弱者でも絶体絶命の窮地に追い詰められれば、強者へ反撃して立場が逆転してしまう場合があるのです。
権力者の口を借りる
言葉っていうのは「何を言ったか」は、さほど重要ではありません。むしろ、誰の心にも響きません。重要なのは、「誰が言ったか」です。
自分が言っても話を聞いてくれない相手には、権力者もしくは、その相手にとって有利になる人物から、自分の意見を伝えて貰えば良いのです。
まぁ・・・あくまでこんな手もあるよって事です。
最後に
 ヒカリ
ヒカリ ナメリーヌ
ナメリーヌ ヒカリ
ヒカリ